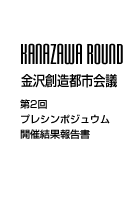
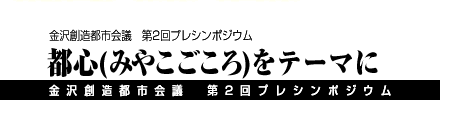
| ■ゲストプレゼンテーション | |
 |
●荒川哲生 金沢ラウンドにご招待いただきまして、大変に光栄に思っております。僕が最初に口火を切るというのも妙な感じがしないでもないのですが、考えてみますと都心(みやこごころ)という言葉がありますが、シェークスピアがハムレットに「演劇は社会を映す鏡だ」というせりふを言わせております。そこに住んでいる人たちの心の動きを映す鏡としての演劇と考えれば、私がトップランナーを務めるのも理由のないことではないのだと思いまして、ほんの少しだけおしゃべりをさせていただきます。 私はいろいろなことをやってきましたけれども、演劇のうえで最終的に自分に与えているテーマというのがいわゆる地域の演劇というもので、少なくともこの5〜6年演劇界ではその地域演劇の問題ということが語られるようになってきました。これはよく誤解されるのですが、「地域の演劇」というと「地方都市の演劇」というようなかたちだけで受け取られているのです。しかし、私に言わせますとこれは本質的誤解で、地域演劇の根本というのは演劇史を読んでいただくとわかるのですが、「地域共同体と共同社会と演劇活動の有機的な関係」、これは実は本日、田中先生がいらっしゃっていますので大変にお詳しいのではないかと思います。江戸時代まで町における演劇活動というのは、非常に共同体という有機性を持っていたのです。 それで歌舞伎の評論家で、もうお亡くなりになりましたが、戸板康二さんという方がいらっしゃいます。その方がちょうど私が文学座という劇団に入った昭和26年にお出しになった歌舞伎についての啓蒙書が1冊ございまして、その中で江戸時代歌舞伎は空気や水、あるいは日光だったかもしれませんが、そういうものであったということを書いていらっしゃる。一番理想的なのは、「演劇という言葉が使われない、自然に生活の中演劇というものがあるという状態」です。この明治以来を考えますと、そういう記憶を失ってきた芸能、あるいは演劇というものの社会におけるあり方、有機的なあり方というものを失ってきた130年でなかったかと僕は思っています。 そのことを最初に気づかされたのは、実は、東京オリンピックの前の年に初めて、フォード財団の招きでアメリカに演劇の研究ということでほぼ1年行ったのです。そのときに、アメリカは申し上げるまでもなく新しい国ですから、そういう伝統は一切ない。ただアメリカの演劇人、それから市民たちもヨーロッパというものを見ていて、ヨーロッパの町には確かに昔からプロフェッショナルの、いわば芝居小屋が非常にたくさんある。それを夢見ていたということなのでしょうか。パイオニアは、前世紀の終わりころにアメリカの場合もそういうことを盛んに言っていたのですが、第二次世界大戦が終わってから急激にその活動が具体的になっていきました。私がここ約40年近くアメリカというものとつきあってきましたが、たったそれだけの間にアメリカでは変化があった。かつては、ロスに住んでいてもプロの芝居を見ようと思うとニューヨークにまで行かなければならなかったのです。これは大陸横断ということになるのです。私は冗談に「演劇的後進国アメリカ」というようなことをよく言ったのです。ブロードウェーというものがあるものですから、皆さんは私の真意はわかってくださらなかった時代もありましたが、ここ数十年で、ほとんどの町がプロの演劇活動をもちろん持てるところまでもっていった。当事者たちも、「これはほとんど奇跡だった」と言っております。 それにはいろいろな理由がありまして、私はいろいろ調べて紹介するというようなことをやってきましたが、いずれにしましても演劇界だけの中の話でなかなか一般 的な関心を呼ぶというところまではこなかったのです。私もそういう紹介だけではなくて、どこか日本の東京以外の町で適当なところがあれば、ほんのささやかだけれどもそういうことの種蒔きをやってみたいと思いまして、10年前にここにまいりました。大体、年の半分を金沢ですごすような生活をこの10年続けてまいりました。いろいろなあるのでしょうが、この辺であとは分科会でと思います。 |
福光松太郎
荒川哲生
川勝平太
竹村真一
田中優子
野村万之丞
松岡正剛
大場吉美
金森千榮子
小林忠雄
佐々木雅幸
水野一郎
米沢 寛