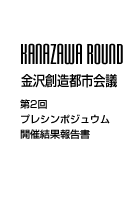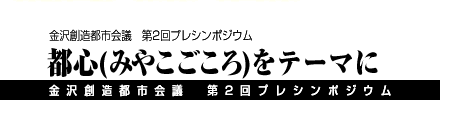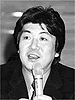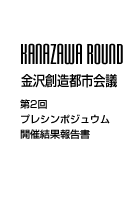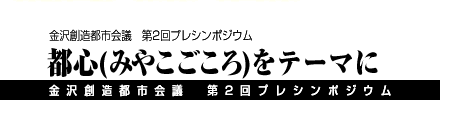|
●野村万之丞
仕事柄たぶん皆さんの中で一番日本中、世界中をどさ回っているのは私ではないかと思います。大体駅や空港に着いたら、劇場に行くか、会館に行くかで何かどこかへ行って、必ず夜になると表に出て飲み屋街をうろうろして、酒を飲んで二日酔いになって帰る。ここはどこなのだ。練馬もパリも金沢も同じかと、案外同じだったりするのですが、食だとか匂いとか空気とかいろいろ違うと思うのです。この1か月もずいぶんいろいろなところに時差ボケしたまま行っていました。例えば地中海のカンヌというところに行った翌日に、バルト海のロストックというすごいところに行くのです。温度差30度です。ヨーロッパの人はあっち行ったり、こっち行ったりする。それは都市をまたいだりしているのです。
都市には顔があるのではないかと、僕らは思います。今はもう廃版になってしまったイタリア人の本に『マルコ・ポーロの見えない都市』というのがあって、私はそれでずいぶん都市のことを考えさせられました。それはどういう本かというと、マルコ・ポーロがフビライ・カーンとしゃべりながらシルクロードを渡っていくというものですが、1ページに一つしかテーマがないのです。「都市と記憶」とか、「都市と喪失」とか、「都市とジョーク」とかとなっていて、その特徴は「そこから3キロ行くと」とか、「その日から3日たつと」というように中心の場所がない。どこからという中心がなくて周辺のことをずっと語るのです。冗談の話をしたり、いろいろな話をしたり、そこへ行くと洗濯物が40枚かかっていて、それが青空の中にぱっと消えてどうしたとかということなどが書いてあるのですが、ずっと1冊読んでいくと、マルコ・ポーロとフビライ・カーンが話してシルクロードを通
っているといっているのですが、どうしてもベネチアの中をぐるぐる回っているようにしか読めない。つまり、いろいろ多くのことを考えるのですが、一つの町の中にある多義的な話題や状況が、即世界中が抱えている都市の問題と同じだということをたぶん言いたかったのではないかと思いました。
そこで私は都市のことを考えるときに、都心のこころは中心の「心」ですが、中心から都市を考えるのではなくて、周辺からものを考えるとなんとなく都市ができてくる、中心がやがて出来上がってくる。鉛筆の周りの方を考えると、急に芯が出てくるのと同じようにした方がいいのではないか。中心から考えるというものの考え方はあまりしないということを、そこで学びました。
それから自分の専門なのですが、仮面のことをやっています。仮面をやるのをチェントロマスケラ、仮面
の中心という言い方をイタリアやフランスでは古典で言うのです。仮面
には3種類あって、私たちの専門の俳優が使う顔につける仮面、演じるために変身する仮面
。それから、鬼門を鎮めるといったような何か呪術的な意味を持ったりして飾っておく仮面
、そして最後が都市を覆う仮面です。都市というのは仮面と同じように表情があって、きちっと顔を表している。ですから、都市を仮面
に見立ててみると、この辺が口で、鼻で、耳でというと五感すべてが必要なわけですから、これが必要でこうということは言えない。私はその仮面
の中から、都市には大事なものは、顔で人間はその人の名前を憶えたり、人格をまず判断するわけですから、都市はまず顔になるようなものを作らなければいけないということを少し学んだしだいです。
それから三つ目は本職になるのですが、中世という室町時代を中心にしたものも、今、田中さんがお話になった江戸時代もそうですが、大都市、今でいうと大芝居、大都市の芝居です。それから先程お話に出ましたが地域の芝居、こういうものを地芝居と言いますが、地元のところにくっついている芝居、それから大きな芝居(大芝居)と地芝居、この間に小芝居というものがあるわけです。つまりツールにあたるもので、大都市のところで生まれたり、人気を博したものがツールとなってどさ回って地芝居になる。そして地元のところで使ってみる。また、地元で非常に受けていたローカルな話題をグローバルなところへ持っていくと。このツールの小芝居というのが江戸でも非常に大事でしたし、中世ではくぐつとか絵解きとか猿楽など、大体流浪芸人とか、あまり職業としてはよくない女性たちが転々と町中を歩きながら流通
して、その都市、都市を結んでいったと思うのです。その三つ目のツールになる流通
ということが都市には非常に大事なのではないかと、自分の経験上から思いました。
結果は何を言いたいかというと、都市というのは人が集まらないとどうしようもないので、テーブルラウンド、テーブルのところで円卓会議を100回しても人が集まらなければ都市などできないわけで、まず集まってきてからそろそろ考えるかということも片方、私たち現場屋にとって大事なことです。
竹村さんが先程おっしゃっていましたけれども、「経済を中心に考えていくよりも、文化を中心に考えるということが21世紀にはまちがいなく大切である」ということは言うを待たずです。そして、文化というのは形を変えて本質を伝えるものですし、もっと言い替えれば、文化・芸術は時間とお金の無駄
ということで、田中さんのおっしゃった大きな庭や公園がなければお城は建たない。
金沢は私ども先祖の土地ですが、私の先祖も金沢を捨てて東京へ来たわけです。私のひいじいさんにあたるのですが、ひいじいさんはしょっちゅう「無駄
はいやだ」と言っていたそうなのですが、とても許しがたい先祖なのです。私は少し無駄
作りにやってきた方が都市はいいのではないかと思っています。
|