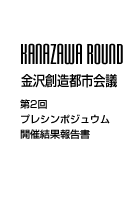
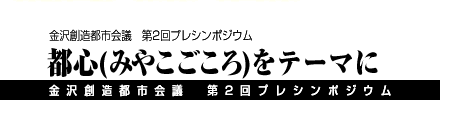
| ���S�̉�c�u�s�S�̑����v | |
| �`�F�A�}���@���X�؉�K �p�l���[�@�@�r��N���A�쏟�����A�|���^��A�c���D�q�A�쑺���V��A���������A �@�@�@�@�@�@���X��Ďq�A�����Y�A�đ� |
|
 |
���đ��@���͋���ɋA����17�`18�N�܂��Â��������Ă��܂��āA�����Ƀm�E�n�E������̂��Ȃƍ��o���Ă����̂������ɂ�����������܂����B�Ȋw�Z�p����Z�p�̔��B�Ƃ����̂́A����ς����How����
�p���Ȃ��A��͂�What����l���邵���Ȃ��ƁA�܂��ɂ��̂Ƃ��肾�ȂƎ����������܂����B �@ �����ɍ��A���͐V��ʃV�X�e�����̉\��������Ă܂�����ǂ��A���̌�� �V�X�e�������̈�̒P�ʂƂ��Ċ����������킯�ł����A�����ɎԂ̃G���W�����߂������ɕς��Ƃ���A���̊�����̐���Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ�킯�ł��B���������Ӗ��ł́A��͂肻����������Ō�� �V�X�e�����l����̂ł͂Ȃ��āA��͂���������������悤�ɂ����ɏZ��ł���n��Z�����ǂ̂悤�Ȓ��ɂ��悤�Ƃ��A�ǂ̂悤�ɒ����f�U�C�����悤���Ƃ������Ƃ�I������A�����������@���Ƃ�Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�������A�����ɂ���Ă���҂Ƃ���ΏZ���`���Ƃ����͈̂�ԓ���Ƃ���ł����A������C���^�[�l�b�g�Ƃ����A�������͂�Ȋw�Z�p�ł����A������g���ƍ��܂Ŕ������Ȃ������������r���[�Ȕ����ł����낢��Ȃ���ɕt�������Ă���܂��B���������Ӗ��ł́A���܂łɂȂ��F����̋C�����Ȃǂ킩���āA���_���Ƃ��A���_�^���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA���Ƃ��s���`���܂Ŏ����Ă�����悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��\���킩�点�Ă����������Ƃ������Ƃ����ɂƂ��Ă͂悩�����ł��B �@ ������́A���Z�p�̖��Łu�|�X�g�C�b�g�v�Ƃ������Ƃ������܂����B��������ɂ������낢�Ǝv���܂��B���̋���̒��ɂ��ꂼ��̗��j�����������̂Ƃ��X�g�[���[�����������̂���������B�����ɂ��낢��ȋ́u�|�X�g�C�b�g�v��t���āA���ꂼ��g�ѓd�b�̒[���ɂȂ�Ƃ���A����ɋ߂Â��Ƃ��̏ꏊ���̏ꏊ�ł��̏ꏊ�̃X�g�[���[�Ȃ�A���j�Ȃ肢�낢��Ȃ��̂������Ă���A������������B����͏���ӂ�Ă��鎞�ゾ����ǂ��A����ł����Ƃ������A�����ɗ��Ȃ��ƌ����Ȃ������B���ꂪ���ɂ������낢�B�Ƃ���A����ɂ͂��낢��ȂƂ���ɂ��낢��Ȃ��̂���������܂�����A�������قɂł���\��������B�Ȃ�قǂ�������Ɛ̖l��u�`�i�]�j���v�Ƃ������ƂŁA�Â����̂��`���̂܂܂Œ��g��V�����ƌ����Ă��܂������A����ȏ�ɂЂ���Ƃ����炻�̋Z�p���g�������Ƃ������낢��ԁA���S�̂�����������Ԃɂł���B �@ ���������Ӗ��ł́A����ɂ����낢��ȂƂ���ɂ��낢��Ȃ��̂���������̂Ŕ��ɂ������낢���݂ɂȂ邩�ȂƁA�����������Ƃ������Ă��������܂����B���ɂ������납�����ł��B �@ �@ |
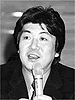 |
�@ ���쑺�@������Ԋ�����̂ł����A�Ⴆ����≽����V��������ɂ���Ƃ����̂́A��ԗL���ȂƂ���ł����ƃs�[�^�[�E�u���b�N���u�t�f�B�m�[���Ƃ����̂��t�����X�Ɍ���������Ă��āA������p�����ƂƂ��Ă��̂ł��B���邢�́A�A���A���k�E���j���[�X�L���Ƃ����̂����q�ɁA�J���e���V�������ŋ������ɂ���B�����g���~���m�̃r�A�`���[�U���R�����e�B�Ƃ����Ƃ���ɋ�������āA������2�N�قǃA���Z�i�[������Ƃ����̂��o�c�������Ƃ�����̂ł��B�ł��A���߂ł����B�Ȃ����߂��������Ƃ����ƁA���̌���ɍ��킹�ăA�[�e�B�X�g�������ԂƑΘb���Ȃ���A���A�D�q��������������悤�ɔ��p�W���������V�A�g���J���Ȃ��Ƃ�����Ă���̂ł����A���ǁA��̓_�ł��߂Ȃ̂ł��B �@ ��́A�����ȊO�ł͂ł��Ȃ��̂ł��B�����ȊO�ł͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���̒��₻�̃p�g���l�[�W������l���������̂��Ƃ�O��I�ɉ������āA�w���ɂȂ��Ă����Ȃ��Ƒ����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B��������ƁA���̃A�[�e�B�X�g�����Ɏ����Ă������Ƃ���Ǝ���œw�͂��Ď����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���x�A�ǂ��������Ƃ����n�߂邩�Ƃ����ƁA����Ƃ��Θb���Ȃ��B�L���O�����ƑΘb����̂ł��B���܂��̎ŋ���20�L���ō��Ƃ��B�Ȃ��A20�L�����Ƃ����ƁA��s�@�オ�G�N�Z�X��20�L���ȏゾ�Ƃ�����̂ł��B�l�炪�����Ă����Ƃ��ɂ́A20�L���̃J�o���̒��Łw�I�C�f�B�v�X�x�����Ȃ����B���ꂪ�ł���̂����炵�����o�Ƃł���A�������҂ł���ƁB���̂悤�ɍ��x�̓L���O�����Ƃ��܂��͑Θb������Ƃ������ƂɂȂ�B �@ �Ⴆ�A��s������ɂ���Ƃ��A���������ɂ��Ă��̒��Ŋ����������邱�Ƃ͔��ɂ������ƂȂ̂ł����A����Ȃ�̃o�b�N�A�b�v�V�X�e���A���̌|�p�Ƃ���������Ȃ������̃o�b�N�A�b�v�V�X�e���������Ȃ��Ɗ���̘_�ŏI���̂ł��B�����łȂ��ƌ��ǁA���������ł����A�ŋ�������Ƃ��ɂ͕�����قƂ������Z���^�[�Ƃ��A�����̂Ȃ��悤�ȂƂ���ɂ��������Ȃ��悤�ȑ��ړI�z�[���Ƃ����̂ɍ��킹������������Ȃ��Ă͂����Ȃ��B���̌o�����ƕ����z�[���ł��̂͂��₾�B�ł͓����������������Ă�����͉̂����Ƃ����A���Ɛ_�Ђł��B�_�ЂƂ����͓̂����`�Ԃł�����B�ł�����_�ЂŖ�O�ł���A�ǂ̐_�Ђ֍s���Ă��������Ƃ��A�ǂ��̎��֍s���Ă���̉�L�̌`�͓������Ƃ��Ƃ����A�O���[�o���Ƃ͌����܂��A�������L���������Ă�����̂ł���Ȃ���ŗL�����������ɂ��Ȃ��ƁA�����Ɠ��Ƃ��������������Ɛ������Ȃ��B����͈�_�v���܂����B �@ ���ꂩ��|������͑�ςɂ��������Ƃ�����������Ă��܂��B���[�N�E�F�A�Ƃ������̂��A�ł́A����̎s��������̌|�p���łł���̂��Ƃ������Ƃ��ɁA�V����w���~���Ă���Ƃ��A�O�����͂ǂ����������ƌ����Ă���̂ł����A���ǁA����͂����ꕔ�̐l�Ȃ̂ł��B���N�A���������Ղ̃v���f���[�T�[��������̂ł����A���������Ղ͕� ���u��l�̊w�|��v�Ƃ����̂ł��B�����̑S����z�e���̉��Ɍ����Ă���̂����āA�����������w�|��̉��ɂȂ�̂��낤�ƁA�ォ�炸���ƌ��Ă��āA���������A���������ƌۂ�ł������āA�O������e���āA�ǂ�ǂ���{���x���ǂ��o����āA�V���x���u�ς��Ƃ����ł肠�v���ǂ�ǂ��Ă���킯�ł��B���������ŋ��������̏��ŋ��Ƃ������̂����܂�Ă���̂��낤�Ǝv���܂��B �@ ��������ƁA���܂ł̎�����A�����J��[���b�p�ɋ��߂Ă��A�A�����J�̗��j��200�N�����Ȃ��̂ł��B�l�̉Ƃł���300 �N����킯�ł��B�Ƃ���ƁA�����500 �N��1000�N�̗��j�������Ă���̂ŁA�������낻�뉢�ČX����`�̂悤�Ȃ��Ƃ͂�߂āA�I���G���^���h���}�c���M�[�Ƃł������̂ł��傤���B������������[�N�E�F�A�ŁA�q�ǂ������ɍ��������u�˂���v�Ƃ��u���ށv�Ƃ��A�������������ƃA���\���W�[�I�Ȃ��Ƃ�������@�ւƂ�����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����C���A���Ɍ���̏ꍇ�ɂ͂��܂��B������A�l�͉����Ƃ������t�͈�Ԍ����ł��B�����Ƃ����ƁA�����̐��E�ɂ��܂����A�����������B�������A���������w���S�́A���͂���������܂킵�āA�����|�p�����Ă���Ƃ����悤�ȁA��������ɂႭ�ł������Ă�肽���Ƃ����C�ɂȂ�悤�ȁA�����������Ƃ̉Q���̒��ɂ��Đi�܂Ȃ��B����͌���őO���ɂ���l�ԂƂ��ẮA����������ɂ��Ȃ��Ƃ��̂��������Ă�������Ȃ��Ȃ邼�Ƃ����ӂ��Ɏv���킯�ł��B �@ �|�p���ɂ͎f���܂������A�|�p���̎g��������ɂ��܂��g���Ă���������Ƃ͎v���̂ł����A���̎��ɏo���Ȃ����R�Ƃ����̂͂���Ɠ����P�[�X���S���̂ǂ����ɂ������肷��B������ǂ��܂ōs���▯�Ԃ��x���Ă��������Ƃ����A����r�W�������Ȃ��̂ł��B�s�[�^�[�E�u���b�N�Ƃ����l�ƃA���A���k�E���j���X�L���͔N�����Ƃ������āA�\�Z������Ă���B������3�`5�N�Ԃ̃r�W�����𗧂ĂāA���̎ŋ���5�N��ɂ͂ǂ��Ȃ邩�A�����Ăǂ��ł��邩�炢������悱���Ƃ��A���������v��������l���o���Ƃ��|�p�Ƃ��o���Ă����Ȃ��ƁA�����E�l�̉�����̂悤�ŁA����͂��ƁA��������ƍ��x�A�W��������Ɣ��p�Ƃǂ����̒D�������ɂȂ�܂��B���ꂩ�牉�������Ɣo�D�����̒D�������ɂȂ�B�ǂ������Ă���Ă���A�ǂ��͕ߏo���Ƃ��A��������Ɠ����悤�Ɍ������n���̂Ƃ���ł�����5�匀�c������Ă��Ă��̌��c�����Ƃ��߁B�����ŏ����ꂪ���������Ƃ���ł��n�߂�B�����ꂪ���x�A�V��������ɓ��荞��ł���Ƃ���͂��߂ƁB �@�@�\�y���̒�������Ƃ����̂́A����͂����Ԃ����I�Ȃ̂ł��B�\�y���̒��A�ڕt���Ƃ����̂��ۂ�Ǝ���̂ł��B����͖��É��ł�����Ƃ��ɂ́A�\�y���̒������ƁA�\�y������́u�M�l�A���J�����v�ƁA���c�[�]����𑊖o�̓y�U�̏�ɂ̂���A�̂��Ȃ��Ƃ����������Ƃ������ŌJ��Ԃ����̂ł��B���������R���x���V�����Ƃ��ė��p���Ă���Η�������x������Ă���A�������͏��ŋ��̕����Ƃ��Ă͔��ɕ֗��ȏ������Ǝv���Ă���̂ł��B�������͊��S�ɖk���O�Y�V���[�ɂȂ�܂����B��������ƁA�̕���������Ă���A�͂��A���|���o�Ă��܂����A���~���[�W�J�������Ă���B�u��������Ă����́H�v�u���l����́H�v�Ƃ������Ƃ̘_���ɂȂ��Ă���B��������ƁA�傫�Ȍ��c�������̎ŋ��邽�߂̋��s���ɂȂ��Ă���B����̕��ւɂ���Č���Ƃ������̂͂ł��Ă���Ƃ����A�����M������Ă��܂��܂������A�l�͂���͐^���Ȃ̂ł��B�����̐E�ƂƂ���������Ă�����̂ł�����A���������̂����z�ł��B �@ |
 |
�@ ���r���@�����ɐ\���グ��ƁA���̍ŋ߂̉����I�S�͂������҂̓��̂̒��ɐ��荞�ނƂ����A���邢�͐��̒��ɐ��荞�ނƂ����A�������������Ȃ̂ł��B�����A�������a26�N�ɏ��߂Đ����t�q����́w���̈ꐶ�x�ł�������イ���ɏo�܂����B���̂������ŁA26�N����30�N�ア���ς��܂ł����Ԃ���{�����܂����B��́A�w�O�����ɉ��I�ɂǂ�ǂ�ω����Ă����B������́A��X�����ۂɎŋ����㉉�����̖��ł��B26�N����ł��ƁA���Ȃ�ւ�҂Ȓ��֍s���Ă��܂��啪�ŋ������Ƃ������̂�����܂����B �@ ����͉��ω��̋��͂������Ǝv���̂ł����A�����{�݂ɕς���Ă����Ƃ��������ŁA������{���ɌÂ��b�ŁA���a38�N�ł����A�V�h�̈ɐ��O�̂����e�̃A�[�g�V�A�^�[�V�h�������A�[��̉��������ƁA�ꉞ���j�I�ɂ͐��̏����ꊈ���̃t�@�[�X�g�����i�[�Ƃ��������߂��̂ł����A���̊ϓ_���瑽���A���܂������Ƃ͐\���グ���Ȃ��̂ł����A���ɕ������Ƃ�����܂��B �@ �悭�O���̓s�s�ŁA�Ⴆ�q���[�X�g���Ȃǂł��ƃA���[�V�A�^�[�Ƃ����̂�����̂ł��B���Ɩ������A��������ł����B�j���[���[�N�ł́A����̓I�t�E�u���[�h�E�F�[�̕��ł����`�F���[���[���V�A�^�[��������I�t�E�u���[�h�E�F�[�̌���Ƃ��Ă͂��Ȃ�Â����̂ŁA���Ō����ƃT�~���G���E�x�P�b�g�Ƃ��A�A�����J�̍�Ƃł��ƃG�h���[�h�E�I�[���r�[�Ƃ��A�O������́w�ߑ�\�y�W�x�̂ǂꂩ�������ŏ㉉����Ă��܂��B����ʼn��ƂȂ���������C���e�B���C�g�E�V�A�^�[�Ƃ��A��������������ɂƂӂƎv���o�����̂ł��B������o�Ă��܂����悤�ɁA�|�p����Pit2�Ƃ����̂����ɂ������낢�B���ۂɃA�����J��[���b�p�֍s���Ƃ�����ł�����Ƃ����X�^�C���ł����A���{�̎ŋ����㉉����ꏊ�Ƃ��Ă͔��ɂ������낢��Ԃł��B���Ƃ̂����̖a�щ�Ђ̑q�ɂ����̂܂܈�ؐG��Ȃ��ł������Ƃ����A����͐���搶�̂��d���ł��B �@ �����������̂𒆐S�ɒu���āA�����̂��ꂱ���H�n���ł��낤�Ɖ��ł��낤�ƁA���邢�͒G���̏��X�X�ɂ��邱�̊Ԃ܂ŋg�{���g���Ă����Ƃ���Ƃ��A���������Ӗ��ŏ�����ɂ�����������K�v�͂Ȃ��̂ł��B�ނ������A�|�������[�N�E�F�A�Ƃ������Ƃ�����������Ă��܂����B�V�A�g���J���E���[�J�u���E�F�A�Ƃ��Ă̈Ӗ��ł͋@�\���Ȃ��Ă͂����܂��A�ǂɉ����Â�Ƃ����K�v�͑S�R�Ȃ��B���������������70�Ȃ���ő�300�Ȃ��炢�܂ł̊Ԃ̂��̂��A�ǂ���s�S�ƌ��邩�͕� �ɂ��āA10�������炢�����Ă������̂ł͂Ȃ����B �@ �����ɂ́A���͊�Ƃő�������������������Ԃ��A�Ⴂ�l�����̉��y�̂��߂Ɏg���Ă���悤�ȏꍇ�������悤�Ȉ�ۂ�����܂�����ǂ��A���������R�ɂł���悤�Ȕ�r�I���^�̌����10�������炢�ӎ��I�ɂ����Ă����Ƃ������Ƃ��������낢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B �@ ���݂̋e�쏬�w�Z�̏ꏊ�ɐ��ŋ��Ƃ����A�Ґ�̐��Ƃ����C���[�W�ł��傤�ˁB���ۂɂ������ɒn�����A�o�X��Ő��Ƃ����Ƃ��낪����悤�ł����B���m�ȔN�x�͖Y��܂������A�������ɍ]�ˎ���̌���ɑ匀�ꂪ�������悤�ł��B���̓����̋��s�A���̂ǂ̌�������A���c���Ă���f�[�^������Ƒ傫�����ꂾ�����B�����Ǝŋ������̕��i�̎����������Ǝc���Ă��܂��B����ŋ���ł̉̕���́A���͂�������j�Ƃł͂Ȃ��̂ł����A�l�����ׂ�������ł����ƎO�s�ɑ������炢�̏㉉������Ă����ƁA����͂͂����肵�Ă��܂��B |
 |
�@ �������@���낢�날��܂����B�����ł��ˁA�S�R�Ⴄ�b�����܂��傤���B���ǁA�n���s�s�Ƃ��A�s�i�݂₱�j������ɂ̓\�[�V�����L���s�^�����邢�̓J���`���[�L���s�^���̂悤�ȁA���܂ł̃v���C�X���J�j�Y���ł͂Ȃ��āA�Ӗ��Ƃ��l�̂������Ƃ��w�K�����Ƃ��L�����Ƃ��A���邢�͋L�^���Ƃ��A�����������܂ł̉��l�ł͂Ȃ����l���ǂ����邩�Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���̂ł��B���̂��߂ɗV�|������A�x�������A���ߕ������َq���o�Ă���B�������A���̂��َq����ߕ��̌o�ϓI�Ȏd�g�݂Ƃ����̂́A�������s�̌������̂�����ł킩��̂ł����A�o�ς����Ō��Ă��܂��Ƃ����ȒP�ł͂Ȃ��킯�ł��B �@ �쏟���ŏ��Ɍ���ꂽ�悤�ɁA�v����ɖ����ȍ~�A�o�ς����œs�s�������Ă��܂����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���ƁA���ɐ��ߕ��ł��o�ς̒��łƂ炦��Ƃ��܂��������Ȃ��킯�ł��B��������ƁA������ �̕ϊ��̎��_�������āA���ߕ��Ȃ�A�a�َq�Ȃ�A�\�Ȃ�A�̕���Ȃ�|�p�Ƃ������̂��ւ��Ȃ�������Ȃ��A���コ���Ȃ�������Ȃ��B����͌��ǁA�Ӗ��̌o�ϊw�Ƃ������A�o�ϕ����w�̂悤�Ȃ��̂��K�v�ɂȂ�B���ꂪ�ǂ��������ł͂Ȃ����{�S�̂̒��ɓo�ꂵ�Ȃ�������Ȃ��̂ɁA��[�I�ɂ͒��肵�Ă���l�͂���̂ł����A���낵���x��Ă���̂ł��B �@ ���̒x�ꂽ���R�Ƃ����̂͂���������܂��B�C�ɂȂ��Ă���̂́A�ߐ��]�ˎЉ�̂��炵���Ƃ����̂ɒ��ڂ��邱�Ƃ͑厖�Ȃ̂ł����A����������̂悤�Ɋ��S�Ɍo�ώ�`�I�ȎЉ�̒��łǂ̂悤�Ɍ����ւ����邩�Ƃ��A�ҏW���������邩�Ƃ����ƁA���܂�ɂ��ł��������̂ŁA��̂ł��̂������Ƃ͂���10�N���炢�ŊF����킩�����Ǝv���̂ł����A�������]�����ł��Ȃ��܂܂��Ă���悤�Ɏv���̂ł��B�����łނ�����́A�������j����w�Ԃ̂Ȃ�A��͖����̂悤�ɉ��Ă����ĕx������������Ă��钆�ŁA�Ⴆ�Ό��X�ւ̂悤�Ȑl�͗��玮�̂悤�Ȃ�������������Ƃ��A��������5�~���炢�Ŕ��낤�Ƃ������v���Ƃǂ܂����Ƃ��A�̕���͈��]�ƂƂ��ɉ��Ƃ��V�����o�Ŏ��Ƃ��Ƃ������Ƃ��A�v����ɉ��Ă����Ȃ���`���I�Ȃ��̂��ǂ��X�g���O�������̂��Ƃ������Ƃ��A�ᔻ�I�ɂ������w�ђ����B �@ ���ꂩ�炱��͎��ۂɂ̓Z�b�V�����̒��Ŗl���o�������ƂȂ̂ł����A�ނ��뒆���ł��B������܂߂đO�c�ȑO�ƌ����Ă����Ǝv���̂ł����A�����Ƃ����R�~���j�e�B�����{�ɔ��������Ƃ��̊�{�I�Ȃ�����̑g�D�_��o�Ϙ_�A�ȒP�Ɍ����Ό��Ƃ��u�Ƃ����Ƃ������́A���邢�͋{����Ղ�̔����Ƃ������̂��܂߂āA�������߂��āA���ɂ��n�����]�˂����ڂŌ��Ȃ�����A���������炢�������Ƃ������̂Ɉ�x�ڂ�������Ƃ������Ƃ������߂������̂���ł��B �@ ���ꂩ��b���S�R�Ⴂ�܂����A����̃\�[�V�����L���s�^���Ƃ��J���`���[�L���s�^��������ɂ́A��͂�Ӗ��̕ϊ��Ƃ������Ƃ��K�v�ł��B�����ł��̈�N�����炢�Ŏ��̕��ŃV�X�e�����J�����āA����͂������낢�Ǝv���邱�Ƃ��O�X�^�[�g���܂����B�n���s�s�����݂̂₱�Ԃ�ɂƂ��Ă����ɗ����ǂ����킩��܂��A�ȒP�ɏЉ���������Ǝv���܂��B �@ ��͊w�K�V�X�e���ł��B�����2�v���X1�Ƃ������̂ŁA�c���Ɠ��傠�邢�͊e���w�Z�������̏ꏊ�ɂ��Ă����Ă��܂��B�q�ǂ���������̂��̂�C�ӂɎ����Ă��āA���̓�̂��̂̊W������������ʼn�����2�v���X1�ɂ��āA�V�X�e���i�p�\�R���j�̒��ɓ���Ă����B��������ƁA���ɂ���ɓ�̂��̂������Ă��āA����Ɏ����̂��̂�����Ƃ����������N�ɂȂ��Ă��āA���̃����N�̊Ԃ̒��̎������v�킸�����Ă��܂������E�A�����������̂����݂��Ɍ��������Đ���������B�ȒP�Ɍ������������V�X�e���ŁA���ɂ������낪���āA���Ɍc���̗c�t�ɂ��͂��߂Ƃ��ď��w�Z�̃��x���ō��e�X�g������Ă���̂ł����A�����z�������������C���p�N�g�����������̂ł��B����͉����Ƃ����ƁA�ꌾ�Ō����ƁAA��B�Ƃ������̂���ɓ�^������B����ɂ������C�������āAABC�ɂ���Ă͂��߂ĉ����̐���������Ƃ������[���Ȃ̂ł��B �@ ���������̖�̉�ł��l�͑啪�������̂ł����A���Z�����������A���R�_�Ђ��������A�ߍ]���̖����������A�����̈ړ]���������A�|�p������������ǂ��A���̋c�_���S���悭�āA�ł͋ߍ]���ƌ|�p���ƈꌩ�W�Ȃ������Ȃ��̂�����āA����ɂ���������ɉ����Ė��������ĉ������悤�Ƃ����C���ǂ����Ȃ��āA�ȒP�ɂ������Ă���B�Ƃ��낪�A�q�ǂ��͋t�ɂǂ�ǂ����Ȃ��������������낪���āA�������\�͂������Ȃ�̂ł��B�����������߂������Ƃ������A���Q�l�ɂ��Ă������������B �@ ��ڂ̓p�h�b�N�V�X�e���Ƃ������̂ł��B����͓��o�̘A���Ǝn�߂��Ƃ���A���낢��Ȋ�Ƃ̐l���������낪���āA�ŏI�I�ɂ͎O�H�����������Ƃ����̂Ŕ����Ă��܂��܂��āA����6������X�^�[�g�����̂ł��B����͊ȒP�Ɍ����܂��ƁA���̌o�ψȑO�Ɍo�ςƂ����̂������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�l�͋��n�͂��Ȃ��̂ł����A���܂�ɂ��������ꂢ�Ȃ̂Ńe���r�Ŏ��X���n�����Ă��܂��B��������ƃp�h�b�N�Ƃ������̂������āA���ꂢ�ɉ���Ă���B����ōŌ�ŁA���ɂ���Œ��ߐ��Ĕn�����̂��Ǝv���āA�ӂ��Ƃ��邱�Ƃ��v�����̂ł��B�܂�A���ۂɏo�����đ����̂͂��̂��Ƃ���n�܂�킯�ł��B�ɂ�������炸�A���n�̔n���Ƃ����̂͏o���ȑO�ɂ��ׂĔ������̂ł��B�����Ƃ���Ă��Ȃ����炱�̕ӂ����A���Ɍ����Ȃ��̂ł����A����͍l����ƂƂĂ��������낢���Ƃł��B�ȒP�Ɍ����A����ɑS�������𓊗^���Ă���킯�ł��B �@ �������낪���Č��Ă݂�ƁA�n�̂��Ƃ��n�傾�Ƃ��n�ꂾ�Ƃ��n�̌������Ƃ��A�v����ɕ����̃~�[���̂��ƁA���邢�͐l�ׂ̂��Ƃ��ׂĂ��ǂ�ǂ�f�l�̐l�����������āA������Ŕ����l������ł��傤�B�Ƃ��낪�A����ҏW���ĕҏW���Ă�������̂��A�����铖����Ȃ��͕� �ɂ��āA����Ɏ����N����O�ɂ����������Ă��܂��B�����ŁA�u����͂������낢�B����̓l�b�g���[�N�Љ���ׂ����v�ƁA�v����Ƀ��A�����[���h�ŋN����ȑO�ɁA�o�[�`�����ȎЉ�A�ȒP�Ɍ������n�Ƃ��������ȎЉ�ł����A�������{�Ƃ��Ă��ꂪ�ł���悤�ɂȂ��Ă���B��������A����ɑ���悤�ȃp�h�b�N���������āA�����ď�����ɂ����āA����ɊȒP�Ɍ����I�b�Y����������悤�Ȏd�g�݁A�����������̂��������ǂ����Ƃ������ƂŃp�h�b�N�V�X�e�����A��̈�N�����炢�A�N�Z�X�R���g���[������ׂ����Z�L�����e�B�̖��܂Ŋ܂߂ĊJ���������̂ł��B����͑�ςɂ������낢���̂��Ƃ������ƂŁA���A�O�H�Ɠ��o��6�����炢����X�^�[�g���悤�ɂȂ�܂������A��؎��̂��Ȃ��̂ł��B�ł�����A����ł��݂��ɔ��蔃�����ł���A�I�b�Y��������Ƃ������ƂȂ̂ł��B �@ �����܂ł��Ă��낢��l����ƁA���ǁA�������Ƃ������̌o�ω��Ƃ����̂́A�����ł��]�˂ł������ł��Ȃ��Ă��̎���̒��ŁA�V�����C���^�[�l�b�g�AWeb �A�f���o�e�B�u���Ƃ��A���[�����Ƃ��A�����A��p���Ƃ��A�������������̒��ŐV�������Ƃ�͍����ׂ��ł���B���j����q���g�����������Ă������Ƃ͎v���܂����B��������ƁA��������Ȃ����ƌ����܂��ƁA��������͗��\�Șb�ɂȂ�܂����C���^�[�X�R�A�Ƃ������Ƃ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���n�߂��̂ł��B���݂��ɃX�R�A�������āA�G�o�����G�[�V�����������āA���̃h�L�������g���������Ȃ��珙�X�ɖc��܂��Ă����d�g�݂Ƃ������̂�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���ۂɂ́A�������̃\�t�g�̒��ɁA�ȒP�Ɍ����Ύ�`�̗������̂悤�ɁA���Ȃ��̂���Ă��邱�Ƃ͂������낢�Ǝv���܂��Ƃ����̂���������ł����Ȃ��炮�邮����ueBay�v�Ƃ����d�g�݂́A���邢�͎��͂���͉��l�����牿�l�Ƃ����P�� �ŁA�ق��̉��l�ƌ������Ăق����Ƃ����A�O���[���h���̂悤�ȃG�R�}�l�[�̂悤�Ȃ��̂��ł��Ă���̂ł����A�܂��������{�̌���ɂ��������̂ɂ͐������Ă��Ȃ��̂ł��B �@ �����ŁA�O�ڂɃV�X�e���J���������̂��u�ҏW�̍��v�Ƃ������̂ł��B���A�������n�߂��̂ł����A�������݉\�Ȓ� �݂Ƃ������̂����݂��ɂ��荇���B���傤�Ǔ��{�͂��Ă͔ˎD�Ƃ������̂������A���Ă͎��R�Ȃ�������̒P�� �Œn��o�ςƂ������̂��m�����Ă����B�����ĕđ�˂͊撣�����Ƃ��A�F���˂͂��������������Ƃ��A�����������Ƃ�����Ă����B���ꂪ�������ǂ����͐Ό��s�m���̗�̔��ĂȂǂɁA�}�ɑO�s�m�����ĉ����͂��߂Ă���̂ɂ�����悤�ɁA�ӊO�ɂЂ���Ƃ����炠�肤��Ƃ͎v���Ă���̂ł����A�ꌾ�Ō����A���鉿�l������A�����ɋ��X����Ȃ�A�c������Ȃ�A�쏟����Ȃ�A��������Ȃ肪�����I�ȗ����������āA���̃h�L�������g�����̂܂ܕ��ƂƂ��ɁA�F�T�Ȃ�F�T�ƂƂ��ɁA�a�َq�Ȃ�a�َq�ƂƂ��ɂ��� ���Ă����B�������̂ł���A100���炢�̐l�̗������Ƃ��h�L�������g�����c��B������C���^�[�X�R�A�ƌ����Ă���̂ł����A�ǂ�������������Ƃ��d�g�݂ɂ��ăV�X�e���ɂ��ē���Ă����K�v�����낻��o�Ă��Ă��邾�낤�B �@ ���̂悤�Ɏv���āA���߂č]�˂�����ƁA�]�˂̎ŋ��̍��Ƃ��A���ҕ]���L�A�����A�����A���ゾ�ƁA���邢�͂��̒��̖��O���Ƃ��A��̖��O�A��̖��O�Ƃ����̂́A�ǂ�ǂ�C���^�[�X�R�A�̗� �𑝂₵�āA�F�������D�������ĕВ����Ƃ��ߍ]���Ƃ������傴���ςȘg�g�݂ł͂Ȃ��āA���ɍׂ������̕��ߗ͂����Ă��鎞�ゾ�����Ƃ������Ƃ����サ�Ă���킯�ł��B�����A�������������ł��������߂Ȃ̂ŁA���������̐V�����d�g�݂Ƃ��A���͂�����Ƃ肠�����́u�ҏW�̍��v�Ƃ������̒��ň�x�������Ă݂āA�o�Ă������� ���F����ɂ܂��z�낤�Ǝv���Ă��܂��B�������Ă���������A�����ɂƂ�ł��Ȃ����ƁA�܂�����Ă��Ȃ����ƂɁA����Ƃ������̂͂����Ă������������Ǝv���̂ł��B �@ |
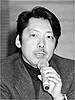 |
���|���@�l���c�_�����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ă��������ɁA�܂��ɏ��������������Ă����������Ǝv���܂��B����A�ꏊ�ɋ|�X�g�C�b�g��\��t����B����́A�����炩�烌�f�B���[�h�̕���������\��t���Ă��������ł͂Ȃ��āA�s�����A�Ⴆ�Β���̐X�̎��Ɋւ��Ă����Ƃ��̖ƂƂ��ɐl���𑗂��Ă��������A�����Ȃ��|�X�g�C�b�g�Ƃ����������œ\��t������悤�ȃV�X�e���������Ă����Ƃ��������z�́A�܂��ɍ��̃C���^�[�X�R�A�����O�Ƃ������Ƃ������Ǝv���̂ł��B�����l�͕��ł͂Ȃ��ꏊ�ɂƂ������Ƃ��l�����킯�ł����A���Ԃ��͏�������͓������Ƃ��Ĉ��ł�����悤�ȃV�X�e���ɂ܂ō��߂悤�Ƃ������Ƃ�������������B �@ ���͂��̂��Ƃ𓊍����čl���Ă݂܂��ƁA�l�͋���̊��S�ہA���邢�͕����S�ۂƂ����̂����Ă����V���Ȋ���̃V�X�e���Ƃ������̂��A�h�C�c�̃G�R�o���N�I�Ȃ������Őݗ����邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B���̂Ƃ��ɗႦ�A�ǂ����̓���̎��Ƃ�����̕������̂悤�Ȃ��̂ɑ����̐l���|�X�g�C�b�g��\��B����͎����̎v������Ƃ��o��������\���Ă����݂̂Ȃ炸�A�\���Ă����Ƃ������Ƃ͂��ꂾ�������Ȃ������������ɗa������Ă����ƍl����킯�ł��B���ꂾ������t����ꂽ�|�X�g�C�b�g�̍��Ǝ��A�� �ɂ���āA�����Ȃ��������a������A���̌����Ȃ��������T�|�[�g����悤�ȃ��A���}�l�[�������V�X�e�����A���ł����ł��Ȃ������I�ȃG�R�o���N�I�Ȃ������Œ��߂�B�G�R�o���N�Ƃ����̂͂������Ȃ����̂��߂ɔO�̂��߂Ɍ����Ă����ƁA���� �̋�s�ɗa�����痘�q���o�܂����A���̗��q�������ԂȂ��̂ł��B�Ⴆ�Ε��� ��2�`3�����q�����炦��Ƃ���ł��A0.5���������q�����炦�Ȃ��B�ł́A���̖ڌ��肵�����q�͉��Ȃ̂��Ƃ����Ƃ��ɁA����͎��͎������]�ފ��ۑS�̑Ώۂł���Ƃ��A���������L�@�_�@�ł��炵�����C���������Ă���A�����������S�ł����������C�������݂������炻��������Ƃɓ����������Ƃ����l���A���ځA���̊�Ƃ̊�������A���������肷��킯�ł͂Ȃ��āA���̋�s�ɗa�������Ă��̗a���̋����̈ꕔ�����������Ƃ���ɓ��������悤�Ɏ����őI�тȂ��瓊���ł���B���q�̈ꕔ�������ɕ�U���邩�����œ����ł���悤�ȃV�X�e���A������G�R�o���N�I�ȃV�X�e���ł���Ă���킯�ł��B�Ⴆ���������������ŋ|�X�g�C�b�g�I�ɏꏊ�Ƃ����ɓ\��t���Ă����āA�����Ȃ������������ɒS�ۂ��Ă����悤�Ȃ������Ō��т��Ă������Ƃɂ���āA����������悤�ȋ���̕����S�ۑ����V�X�e���̂悤�Ȃ��̂��ݗ��ł���̂ł͂Ȃ����B �@ ���ꂪ�K�v�Ȃ̂́A������猾���Ă���悤�ɑ傫�Ȏ���F���Ƃ��Č����ƁA���Y�Ǝ���Ƃ����̂͏ꏊ�Ƃ����n�Ƃ��n�搫�Ƃ����̂͑S�R���Ȃ�����ɂȂ�B�H��Ƃ����̂͂ǂ����ɂȂ��Ă��A�Ⴆ�u���i�b�N�X�v�̂悤�Ƀ}�C�N���\�t�g�̂悤�Ȋ�Ƒ̂������Ȃ��Ă��A���E���ɕ��U�����R���{���[�V�����ʼn������̂������Ă��܂����A���E���̂ǂ����Ŕ������ꂽ���́A���邢�͐��E������C�ɐȌ����Ă��܂��Ƃ������Ƃ́A�{���ɋ���Ƃ����ꏊ�̒S�ۂƂ����̂́A������������悤�ɎY�ƂƂ��o�ςƂ����x�[�X�ł͂��肦�Ȃ��āA�{���ɂǂ����������������邢�͊������������āA���̒n�悪�ǂ�Ȗ��͂������Ă��邩�ł��B���邢�́A������c�_���o�܂������A����u�����h�Ƃ������̂������ď���������Ɖ��Ƃ����܂������B����͈��̗^�M�\�́A�^�M�͂ł��ˁB�M�p����Ă���킯�ł��B����ŃC���^�[�l�b�g����ɂȂ�Ȃ�قǎ����悤�Ȃ��̂��ǂ�ǂ�o���܂�����A�u�����h�Ƃ����T�O�����������L�`�ɉ��߂���ƁA�u�����M����̂����炽�Ԃ����낤�v�Ƃ��A�u���S���낤�v�Ƃ��A�u�M�p�ł��邾�낤�v�Ƃ������^�M�́A���̒S�ۂł��B �@ ������S���Ƃ����悤�ȍ]�ˎ���̍��Y��H���Ԃ��������ł͂Ȃ��āA�]�ˎ���̈�Y�Ɉˑ�����̂ł͂Ȃ��āA�V���������S�ہA�^�M�͂Ƃ������̂��ǂ��������Ă������B���̂Ƃ��ɃC���^�[�X�R�A�����O�Ƃ����{�g���A�b�v�̃V�X�e���A�|�X�g�C�b�g�I�Ȃ�����A�܂��Â���ɂ�����ڂ���킯�ł�����A���ꂪ���Ԃ�q���g�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@ |
 |
�������@���낢�날�肪�Ƃ��������܂����B�u�t�̊F����ɂ��z�����������āA�����č���A�v���V���|�W�E���Ƃ������Ƃł����炩��w���������X�A���邢�͎w�������c�̂̊F����ɂ��z�����������Ă���܂��āA���������Ӗ��ł͔��ɋC�����悭�搶������̓ł𗁂т��킯�ł��B �@ ���̕��������́A����ɑ���Ȃ����̂��Ǝv���̂ł��B�����炭��{�I�ɂ́A���ɐG��ɂ��������������Ȃ��炱�̂܂��Â�������Ă���������Ă���̂��Ǝv���̂ł��B���̐G��ɂ��������Ƃ����̂��A���ƂȂ��T�O�Ƃ��Ă̕S����������A���j��������A�O�c�������肷��̂ł��B �@ �������A�������낻��A���Ō����ƃR�N���o���Ă��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�������肵�����Ă���Ƃ����������A���Ԃ�O�ɓ`����čs���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���������̘b�Ƃ��ẮA�ǂ̂悤�Ȏ�@ �ŃR�N�����Ă������A���̎���̋���������Ă������Ƃ������@�_�ɂ��Ă͂��낢��ƃA�C�f�A�����������܂����̂ŁA�܂��A�F����ƈꏏ�ɉ�����̓I�ɂ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B �@ ���̋��E���h�A����n���s�s��c�Ƃ������̂�2001�N�ɂ͖{�Ԃ��}���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A�����̖�̗[�H���[�ׁA�����č����A�搶���Ƃ��b�����Ă��Ă����Ǝv���Ă������Ƃ�����̂ł��B�Ƃ����̂́A�c�_�������Ă����悤���Ȃ��ȂƂ������ɒP���Ȃ��Ƃ������̂ł��B���_�̕����s���Ă���܂��āA���������̉��Ɋւ��Ă��A���ꂩ�����Ƃ��ɂ����Ƃ����炢���Ǝv���̂́A�~��ɂ͂Ȃ�Ȃ��������Ƃ������Ƃ��Ƃ��A�}�C�N�V�X�e�������܂������Ă��Ȃ��Ƃ��A�������Ƃ������ꏊ�ł�����������肪�������肵�܂����A�� �ɂ������ꏊ�łȂ��Ă��c�_���ł���Ƃ������Ƃ̕����������낭�Ȃ����肵�Ă��Ă���B�����Ă܂��A�c�_���ꏊ��ւ������炢�̒m�b�����o�Ȃ��قǕ��@�_���s�����Ă���B�c�_�����Ă��Ă��A���ꂩ��{���ɒ����ς��̂��Ƃ����ƁA���܂�ς�������߂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��v���Ă���܂��B �@ ���������Ӗ��ŁA������b���o�܂���������g�ݍ��킷�悤�ȕ��@�ɂ��ẮA�Ȃ��Ȃ�����I�Ȃ��Ƃ��낤�Ǝv���̂ł��B�������A�C�f�A�����������Ă��܂��āA�ǂ̎�����g�ݍ��킹��������I�Ԃɍ���قǂ̃��j���[���A����A���ɗ^�����܂����B���Ћc�_�����ł͂Ȃ��āA�������Ƃ��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ����āA���낢��ȍ�����W�܂��Ă����s�s�̐l�����ɂ��A���E�̒��ł��̒n����̎����̏�ł���Ƃ������Ƃ�F�����Ă��炤�Ƃ����̂����Ȃ肨�����낢���ƂɂȂ肻���ł��B��������A���삳������������悤�ɁA�C���^�[�l�b�g�ŃI�b�Y���l�b�g���Ă�����Ă������Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B �@ ���ꂩ������P�́A��̓I�ɐ�����玑���̎g���A���邢�͑��₷�����I�ȉ��l��S�ۂ��Ă����Ƃ����b���o�܂�������ǂ��A�����������Ƃ��{�C�ōl���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�s������Ƃ���̓I�ɂ��̂悤�ȏ̒��ŁA����ȏ�ǂ̂悤�ɂ��Ď������o����̂��Ƃ����Ƃ��Ȃ����ł��B������ǂ̂悤�Ȓm�b�Ő��E���炨�����W�߂Ă������A��������g�����A�����������������E�̓s�s�_�̉����̂��߂ɂ���Ă������킯�ł��B��������������̂������낢���̏�Ƃ��Ă̋��E���h�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��� ���Ƃ��A���ɍ���v���܂����B���N�܂ł͂��̋c�_�̏���ǂ̂悤�ɂ���̂��Ƃ������Ƃ��l���Ă��Ă����Ȃ�Â��Ȃ��Ă����̂ł����A��̓I�Șb��g�ݍ��킹��̂��\���Ƃ������Ƃ��A����A���ɂ悭�킩��܂��āA���̕����Ɍ������Ă������������Ԃ�l���W�܂��Ă���邾�낤���A���낢��Ȓm�b���o�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@ ���ЁA������̕����ł�������������Ă����܂��̂ŁA�搶�����͂��߁A�����Q���̊F�l�ɂ����m�b��q�������Ǝv���܂��B�{���ɍ���͂��肪�Ƃ��������܂����B |
���������Y
�@�r��N��
�@�쏟����
�@�|���^��
�@�c���D�q
�@�쑺���V��
�@��������
�@���g��
�@���X��Ďq
�@���ђ��Y
�@���X�؉�K
�@�����Y �@
�@�đ�@��