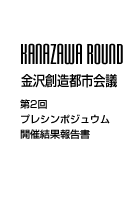
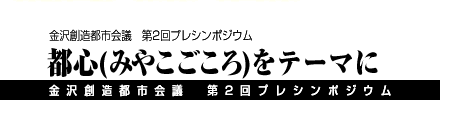
| ■コーディネータープレゼンテーション | |
 |
●佐々木雅幸 ちょうど1年前、この会場で第1回目のプレシンポジウムが行われたときに、その最後のまとめの挨拶の中で、「1回目のシンポジウムの中で私が持っているさまざまな知識やアイデアを全部放電したので、次の1年間はイタリアで充電をしてくる」ということを申しました。その会議の4日後にイタリアのボローニャにまいりまして、1月の末まで約10か月にわたって、主にイタリアの都市ないしはヨーロッパ、アメリカの都市も含めて、20世紀の末からミレニアムにかけての都市がいったいどういう方向に動いているかということに関心を持ち、あちこちを動いておりました。 そこで非常に強く感じたことは、特にヨーロッパはそうなのですが、約200年続きました近代の国民国家の時代が終わりを告げて、明らかに都市の世紀を迎える、都市の時代に再び戻ったといいましょうか、そういう感は非常に強くしております。同時に、先程グローバルエコノミー、あるいはグローバリゼーションという問題が出されたのですが、特にヨーロッパにおりますと現在住んでいるグローバリゼーションというのは何か偏りが強すぎて、特にアメリカの影響が非常に強すぎて、これは本来のグローバリゼーションと言えないのではないかという声が非常に強くなってきておりました。 私は本来、グローバリゼーションというのは、さまざまな都市やあるいは民族が多様性を輝かせながらグローバルな社会を作っていく時代だと思っておりまして、その意味でいきますと、20世紀の末に起こったグローバリゼーションは、やや金融や情報技術に依存をしすぎておりまして、そのために非常に画一的な教育が強く出て、スタンダードばかり強調される。 しかし、これを越えて本来のグローバリゼーションが、必ずやより強い動きとして、強いうねりとして実現するだろうと思っておりまして、そのときに都市のあり方が問われるし、都市の多様性や個性が文字どおり問われてくると思います。都心こそはさまざまなる都市の歴史性を背負ったきわめて重要な精神的な空間、場でありまして、私は創造都市というのは、その都市の中に創造的な場をよりたくさん持っている都市のことだと思っております。 その意味で、次の世紀に向けて例えば金沢という都市が、舞台となって世界の創造都市のあり方についてディスカッションを自由に行えることができる場を提供することができれば、それは大変に幸福なことであると思っているのです。 今日もそういうかたちで進めさせていただきたいと思っております。 たまたま今日はU字型になったせいで、江戸・京都対地元金沢という、そういうご対面 形式になってしまいました。本来もっと解きほぐして、入り交じって、金沢の方も金沢を離れ、東京や京都の方もさらに自由にそれから解き放たれて都市のあり方を検討するという自由な雰囲気のもとに会議が進行していくことを念じております。 |
福光松太郎
荒川哲生
川勝平太
竹村真一
田中優子
野村万之丞
松岡正剛
大場吉美
金森千榮子
小林忠雄
佐々木雅幸
水野一郎
米沢 寛